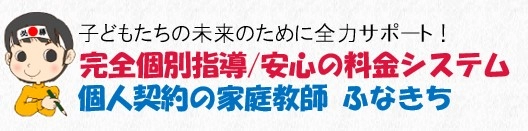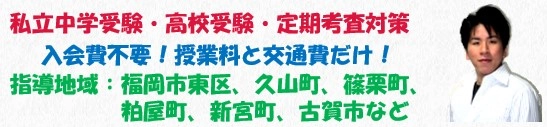ゲーム依存症についての説明と分類
子供が大好きなゲームによる「ゲーム依存症」について、書こうと思います。 今回、取り扱う「ゲーム」とは、主にTVゲーム、携帯型ゲーム機、ネットゲームなどの家庭用コンピューターゲームのことです。
しかし、同時にゲームによる弊害も問題視されるようになりました。 とくに近年では、「ゲーム依存症」が教育や医療において取りざたされています。
私もこれまでに「ゲーム依存症」と思われる子供の指導を何度か経験しました。
中学生でも基本的な掛け算や割り算が出来ない、 小学校3年生以降の漢字が書けないなど、極めて学力が低いという特徴があります。 また、痩せっぽち体型か明らかな肥満体型と、両極端で子供特有の元気の良さに欠ける印象があります。
ゲーム依存による、勉強不足、運動不足、睡眠不足、対人関係の希薄化が原因だと思われます。
このようにゲーム依存によって、成長過程において多くの弊害が引き起こります。 また一度、ゲーム依存を起こすと、なかなかゲーム止めることができません。 たとえ親がゲーム取り上げたとしても、自分で買ったり、友達の家でやったり、 場合によっては万引きなどの犯罪行為をしたりと、問題が大きくなるケースも多いです。
ですから、「ゲーム依存症」は病気だと考え、必要応じて専門機関の受診が勧められているのです。
ここでは、ゲーム依存度を8段階に分類し、対策について考えたいと思います。 以下の分類表は、岩崎正人氏の「子供をゲーム依存症から救う精神科医の治療法」より抜粋。
00段階 ゲームに興味を持たない
0段階 ゲームを欲しがるが持ってはいない
1段階 時々プレーする
2段階 週に2−3回プレーする
3段階 毎日1時間プレーする>
4段階 毎日2時間のプレー+不規則な生活
5段階 毎日3−4時間のプレー+いつもゲームのことを考えている
6段階 ゲームをしないと落ち着かない+不登校、引きこもりなど
青色で表示した00段階から1段階については、ゲーム依存の心配はほぼありません。
オレンジ色で表示した4段階から5段階は、終了時こくの呼びかけなどのちょっとした親の介入が必要です。
赤色の6段階以上は注意が必要です。6段階は「ゲームをするうえでのルール作り」、 7段階は子供をゲームから遠ざける必要があり、 8段階は精神科医への相談、受診を勧めます。
詳細は、「データバンク出版 岩崎正人著 子供をゲーム依存症から救う精神科医の治療法」をご覧ください。
子供の遊びは、勉強や成長に大きな影響を与えます。 また、依存症は、一つのゲームだけ限定されるのではなく、 ゲーム、ネット、アルコール、薬物、ギャンブルなど様々なものに飛び火する場合があるのです。
ですから、ゲーム依存症にならないようにと言った対症療法ではなく、 何かに依存せず生活が送れる「こころの強さ」を育てていくことが重要です。
次回は、ゲーム依存症の予防について書きます。
(2013.10.14更新)